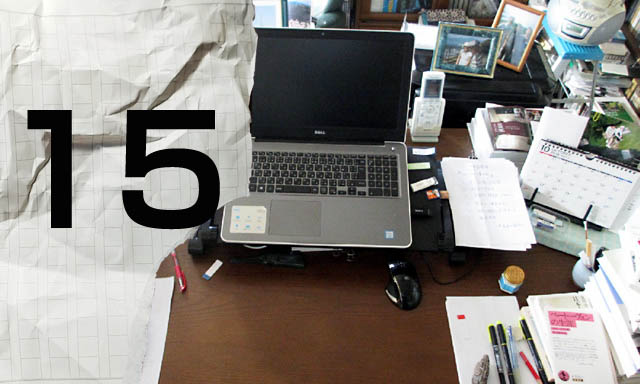小説のいいところは自由ってことだ。何をどう書いてもかまわない。テーマは自由。形式としても自由。長さも自由だよね。数行でもいいし、数十冊でもいい。現実からも自由だ。つまりフィクションってことだ。リアリズムからはどんどん逸脱していく。ある朝目を覚ますと虫になっていた男が主人公でもいい。真面目である必要はない。誇張の自由、非常識の自由、非現実の自由。
ただし、でたらめってことじゃない。自由というのは自分できめるってことだ。ぼくたちの社会でも同じだよね。勝手になんでもやっていいってことじゃない。やっぱり人に迷惑をかけてはいけない。ルールがあるわけだ。小説でも同じでルールがある。つまり「読者に迷惑をかけてはいけない」っていうルールがね。何をどう書いてもいいけれど、ちゃんと読者が付いてこられるものじゃないといけない。
そのために一つの制約を課すわけだ。小説のかたちをきめると言ってもいい。テーマや長さや形式などをきめる。真面目な小説なのか、それとも虫になった男が出てくるような小説なのか。自由にきめていいけれど、どれかにきめなければならない。たしかに選択肢が無数にあるという意味では自由だけれど、そこに一つの制約を持ち込まなければならない。その制約が語り手だ。小説の場合は語り手が、作品のかたちをきめるんだ。
前にも言ったように、小説の三つの要素は作者と語り手と登場人物だ。このうちの語り手が実際に物語を紡いでいく、フィクションをつくり出すわけだよね。語り手の設定の仕方によっていろんなスタイルの小説が生まれてくる。
一人称で書く場合は、語り手と登場人物は同一人物だ。語り手は小説空間のなかにいて、物語の登場人物たちと交わっている。小沼丹さんの「煙」という短編の場合だと、「ぼく」とか「私」といった人称代名詞は使われていないけれど、「いつだったか、寒い日、溜まっていた古い林檎箱とか蜜柑箱を、裏の路に持出して燃すことにした。溜った落葉なら庭の片隅で燃せるが、大きな木の箱となるとそうは行かない」というふうに語っている語り手は作品のなかにいる。だからこのすぐあとで自転車に乗った警官と言葉を交わしたりする。
三人称の「彼」が使われていたら、語り手は物語空間の外にいることになる。カフカの『変身』みたいに、「ある朝、グレーゴル・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した。彼は鎧のように堅い背を下にして、あおむけに横たわっていた」と言う具合に物語をはじめる場合、語り手は作品の外にいる。語り手はあくまで声として、ナレーションをするだけで作品のなかには顔を出さない。
語り手を作品のなかに設定するか、つまり一人称の「ぼく」や「私」で語らせるか。それとも作品の外に設定した純粋な声としてナレーションの役目を担わせるか。これによって作品のスタイルもかわってくるし、描かれる物語の性質も変わってくる。たとえばカフカの『変身』を、「ある朝、おれは気がかりな夢から目をさました。すると自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した」と言う具合にはじめると、ずいぶん印象が変わるだろう? 文体も変わるし語り口も変わる。まあ、このあとどう展開するかにもよるけど、作品の雰囲気はずいぶん変わると思う。
語り手は作品の文体とも密接に関係しているし、語り手の個性(あるいは無個性)によって小説は面白くもなるし、つまらなくもなる。だからどんな語り手をつくり出すかが、ひとつの腕の見せどころでもあるわけだな。