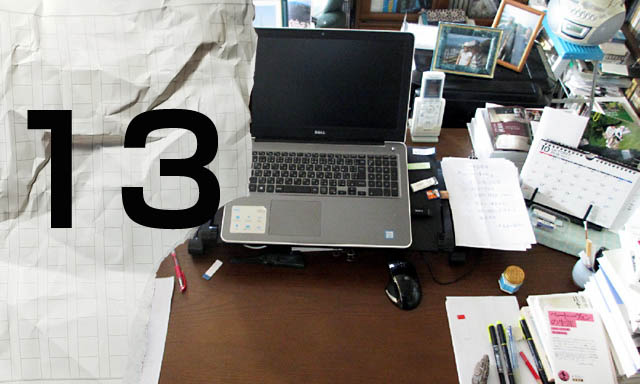新しい小説を書きはじめた。構想はだいたいできていたんだ。あとは書きはじめるだけ。でも書き出しがどうしてもきまらなかった。みなさんにこうやって話をしているうちに、ぼくのなかでもだんだんテンションが上がってきた。そして「よし、いくぞ!」って感じで書いてみた。
わたしを見つけてくれたのはトトだ。職業は医者である。いや、患者も診るサーファーと言ったほうがいいかもしれない。本当は一日中でも波に乗っていたいのだが、さすがに分別のある大人なので定刻になると町の診察所に出かけていく。出かける前に波の乗るのが習慣だ。
最初にわたしの目に映ったのは、砂浜を踏みしめて歩いてくるトトの逞しい足だった。それは白く立ち込めた霧のなかから現れた。早朝の海にはこんな濃い霧がよくかかる。「おや、これはまた可愛い仔犬だ」とトトが言ったかどうか知らない。
カンはトトの子どもで、これはわたしとカンの物語である。自分について書くことはあまりないので、主にカンの物語ということになるだろう。
よし、いくぞってわりには、ちょっと脱力系の出だしだって? まあ、そういう意見もあるだろう。さて、みなさんはどんなことを読み取ってくれるかな?語り手は「わたし」という一人称だ。そして犬である。漱石の『猫』を思い浮かべる人も多いかもしれないね。でも狙いはちょっと違う。犬の目を借りて文明批評をやろうってわけじゃないんだ。
この短い冒頭には、いろんな情報が埋め込まれている。「カンはトトの子どもで、これはわたしとカンの物語である」と語り手は言っている。つまり「カン」という少年が主人公で、「トト」と呼ばれているのがおとうさん、町医者でサーフィンが好きらしい。
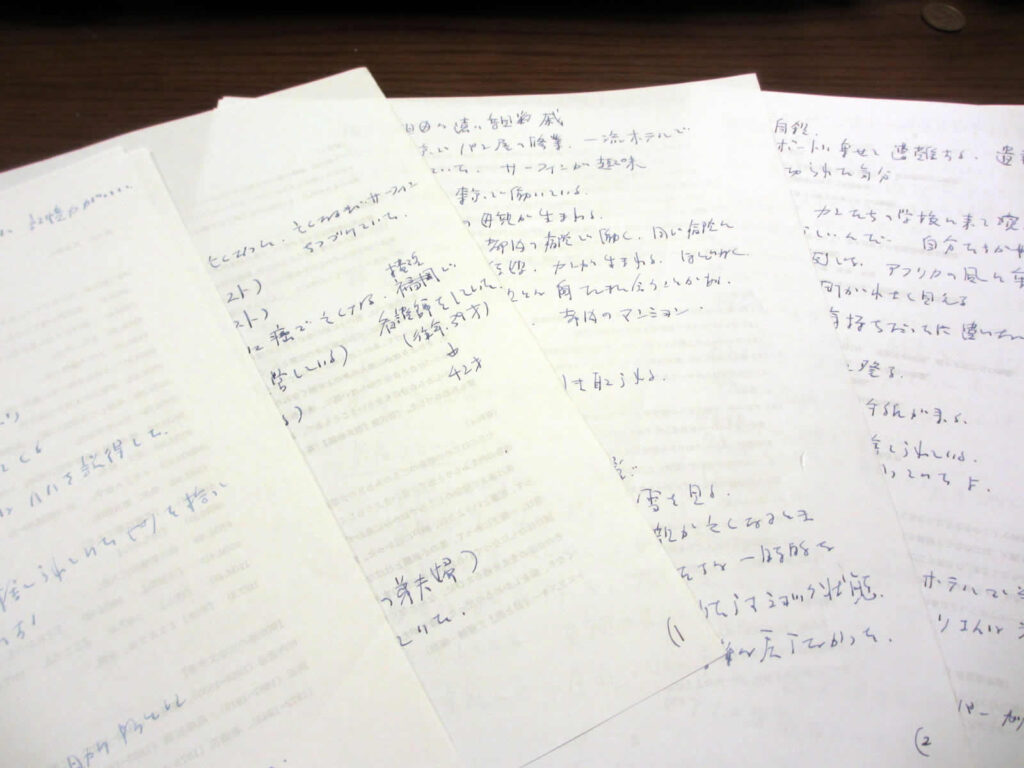
主人公の少年や父親が実名で呼ばれていないのは、犬の視線、犬の言葉で語ろうとしているからだ。語り手の犬にとって少年は「カン」で、父親は「トト」ってことだな。すると語り手と登場人物のあいだにちょっと距離感が出るだろう?ヒトとイヌという種の違いを乗り越えて語っているわけだからね。「勘一は正太郎の息子で、これはわたしと勘一という少年の物語である」では、語りが人間臭くなってしまう。
このあたりが漱石の『猫』との違いだ。漱石の小説の猫は作者の分身であり、作者のもう一つの「眼」の役割を果たしている。猫が喋っていることは、作者である漱石が見聞きしたことだし、自己批評を含めて漱石自身の考えを代弁している。そういう意味で、作者の分身なんだ。漱石が猫の目を借りて人物批評や文明批評をやっている、というふうに読めるわけだな。
それにたいして、ぼくの新しい小説が狙っているのは、むしろ「童話っぽさ」だ。宮沢賢治の童話などでも、よく動物が人間と同じように喋ったり悲しんだりするだろう。ああいう世界を書こうとしているんだ。
ファンタジーとはちょっと違う。ファンタジーは空想や幻想だろう?この小説で描かれる世界は、みんながよく知っている現実の世界だ。でも語り手は犬。空想や幻想ではないけれど、現実そのものでもないってことになるよね。空想と現実のあいだにある世界っていうかな。子どもの世界と大人の世界の中間にある世界と言ってもいいと思う。そういう世界を犬が一人称で語っていく。さて、どんな小説になるんだろうか。ぼく自身も楽しみだ。
写真は小説の簡単な構想やアイデアを記したメモ。以前は創作ノートみたいなものを用意していたんだけど、最近はプリント・アウトしたコピー用紙の裏などに書いたものをクリア・ファイルに挟んでおく。頃合いを見てパソコンに入力し、ときどき思いついたことを上書きしながらストーリーを組み立てていくことが多い。