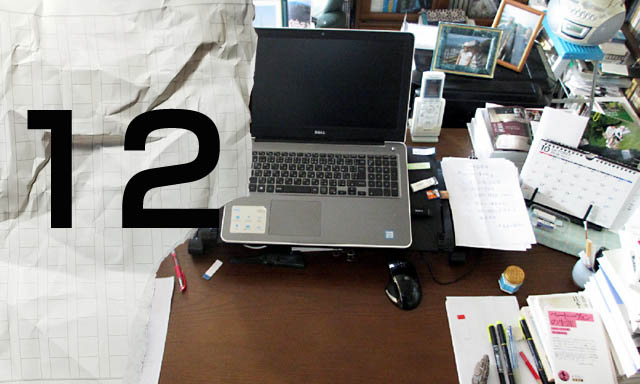前回に引きつづき書き出しの話だ。別の例を挙げてみよう。
一八四〇年九月十五日、朝の六時頃、出帆間際のヴィル=ドゥ=モントロー号がサン=ベルナール岸の前で、もくもく煙のうずを上げていた。 人々は息せき切って駆けつけた。樽や索や洗濯物の籠などが往来を邪魔している。水夫たちは言葉をかけられても返事をしない。人同士ぶつかりあった。荷物が二つの外輪覆のあいだに積まれてゆく。そうした騒がしい物音が鉄板から吹き出す蒸気の音にかき消され、その湯気はあたりをすっかり白っぽい靄でつつんでいた。一方、船首では号鐘がひっきりなしに鳴っている。 やがて、船が出た。そして倉庫や材木置場や工場の並んだ両岸が、二条の幅広いリボンをくりひろげるように走りだした。 髪を長くした十八歳の青年が一人、写生帳をかかえて、身動きもせず、舵のそばにたっていた。
こちらはフローベール『感情教育』の冒頭(生島遼一訳)。最後に出てくる「髪を長くした十八歳の青年」が主人公だってことは推測がつくよね。青年の名前は「フレデリック・モロー」で、大学入学資格者(バシュリエ)の試験に合格して故郷に帰るところだってことは、このすぐあとで説明される。プルーストの場合と違って、この作品では語り手は主人公ではない。語り手は語りに専念して、目に見えない存在になっている。つまりナレーションをやっているわけだな。声に個性がないだろう。非常にニュートラルな、ドキュメンタリー番組のナレーターみたいな声だと思わない? 小説的現実に異質なものを持ち込まないという見識というか、一つの美意識なんだろうね。フローベール自身が確立した「三人称客観描写」と呼ばれるものだ。なんか語り口がすっきりして、クリアな感じだよね。
もう一つ、フローベールの作品に特徴的なのは、語り手がカメラとして機能していることだ。段落が変わっているところは、映画でいうとカットが変わっている。わりと短いカット割りで一つのシーンを撮っているのがわかるよね。最初は遠くから港の情景を撮っていく。つぎに少しカメラが寄って、慌ただしい出帆の準備が描かれる。再び船の遠景。最後にカメラがぐっと近づいて主人公を捉える、といううまい演出だな。
つぎは有名だから、みなさんもご存知なんじゃないかな。

ある朝、グレーゴル・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した。彼は鎧のように堅い背を下にして、あおむけに横たわっていた。頭をすこし持ちあげると、アーチのようにふくらんだ褐色の腹が見える。腹の上には横に幾本かの筋がついていて、筋の部分はくぼんでいる。腹のふくらんでいるところにかかっている布団はいまにもずり落ちそうになっていた。たくさんの足が彼の目の前に頼りなげにぴくぴく動いていた。胴体の大きさにくらべて、足はひどく細かった。
その通り。フランツ・カフカの『変身』だ。少し古い高橋義孝訳。カフカの場合、一つのシーンをワンカットで撮っているのがわかると思う。しかも室内だから、カメラの位置はあまり変わらない。それでも「頭をすこし持ちあげると、アーチのようにふくらんだ褐色の腹が見える」というところはカメラが対象に寄っているよね。
この作品の作者はフランツ・カフカで、主人公はグレーゴル・ザムザ。ここまではいいよね。では語り手は? 作者と語り手の関係はどうなっているんだろう。フローベールの作品ではそのあたりが曖昧だった。作者=語り手、つまりフローベールという作者が三人称で物語を語っていると考えても大きな問題は生じなかった。ところがカフカの作品ではそうはいかない。もし作者=語り手とすると、どうだろう? 作者は嘘つきだということになってしまうよね。目を覚ましたら大きな虫に変身していたなどという荒唐無稽の大法螺には付き合っていられない、ということになってしまう。逆に言うと、『変身』みたいな小説が書けるのは、作者と語り手がきちんと分離できているからなんだ。作者とは別の語り手を設定することで、どんな荒唐無稽な話も、不埒な話も書ける。また宇宙の果ての話や、数千年後の未来の話も書ける。つまりフィクションが可能になるわけだな。
こんなふうに小説の冒頭っていうのは、いろんなことを考えさせてくれる。だからいい加減に書いてはだめだ。どういう語り手を設定するは、小説の基本的な構造にかかわってくることだからね。どういうタイプの、どういう規模の小説を書くかによって、適切な語り手を設定する必要があるし、そこからおのずと書き出しの文体もきまってくる。というわけで、ぼくはいま新しい小説の書き出しをどんなふうにするか、頭を悩ませているところだ。じゃあ、また。