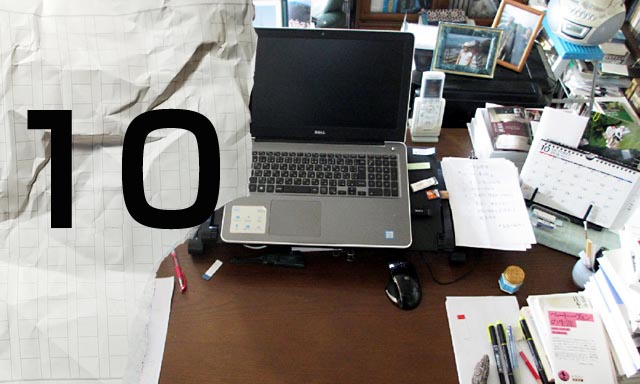1987年に「気配」という作品で『文學界』の新人賞をもらったとき、選考の過程で「古井由吉の文体で吉行淳之介の世界を書いている」という声が出たらしい。それを瑕疵とする選考委員もいたけれど、日野啓三さんや中上健次さんが「まあ、いいんじゃないの」と言ってくれ、宮本輝さんも「おれは、どっちでもええわ」と中立の立場をとってくれたので受賞が決まったらしい
古井由吉の数多い作品のなかから思い入れのあるものをあげてみよう。まず『杳子/妻隠』に収められた「杳子」は、山を舞台にした瑞々しい恋愛小説である。このヒロインは『槿』あたりまで、古井さんの小説にしばしば登場するタイプの女性だ。同じ時期に書かれた「妻隠」は静謐な日常のなかに潜む小さな齟齬を描いたもの。何事もない日常が反復されていくことが、しだいに狂気の色合いを帯びていくというテーマは、『栖』や『親』といった初期の代表作において一貫して追求されることになる。

ちなみにぼくが「気配」という作品で『文學界』の新人賞をもらったとき、いちばん影響を受けた作品が『栖』だった。そのころ(1984年ごろ)『親』を読んですっかり感心したぼくは、前作にあたる『栖』を読みたいと思ったが、平凡社から出ていた単行本はすでに手に入らなくなっていた。それで『栖』が収録されている河出書房新社の古井由吉作品集「五」を3500円も出して買ったんだ。フーコーの『言葉と物』(新潮社)が4000円、金子武蔵訳のヘーゲル『精神現象学』は上巻が5000円、下巻はなんと9000円もした。でも卒業論文を書くために食費を切り詰めて買ったもんだよ。ああいう健気な情熱、いまはもうなくなったなあ。
時代は前後するけれど、1980年から1983年にかけて「作品」と「海燕」に連載された『槿』(「むくげ」ではなく「あさがお」と読みます)は古井由吉の源氏物語と言っていいだろうね。集英社の「青春と読書」に連載され1982年に単行本化された『山躁賦』は、ぼくのいちばん好きな作品だ。いまでも古井さんの最高作ではないかと思っている。1989年の『仮往生伝試文』は出てすぐに買い求めた(これも3000円だった、トホホ)。一気に読んで「すごい!」と思ったけれど、以後はほとんど読み返していない。久しぶりに読んでみようかな。いつものように装幀は菊池信義で、彼が手掛けた古井さんの本ではこれが最高じゃないかしら。ぼくも一冊だけ角川書店から出た『ジョン・レノンを信じるな』の装幀が菊池さんである。いまとなっては貴重だよね。担当編集者の根本さん、ありがとう!
なかなか先へ進まない。1990年前後から『楽天記』『陽気な夜まわり』といった独特の老境ものが書かれる一方で、『夜明けの家』(1998年)のように、老いのなかにきわどい色気を織り込んだ艶っぽい作品も書かれる。これも古井さん独特の味だが、このころの作品でぼくがいちばん印象に残っているのは、エックハルトなどの神秘主義を題材にした『神秘の人びと』(1996年)である。やはりムージルやリルケを翻訳してきた人でないと書けない文章という気がする。
最後に古井さんの小説以外の作品についても短く触れておこう。まず深い洞察に富んだ多くのエッセーがある。しかし晩年の古井さんの小説は、どれも深い洞察に富んだエッセーみたいなものなので、ここでは若いころの『山へ行く心』をあげておこう。タイトルのとおり山にまつわるエッセーだ。若いころの古井さんは山登りが好きで、「男たちの円居」や「杳子」、『聖』などには山登りの話が巧みに取り入れられている。ぼくも山を舞台にした小説を幾つか書いたけれど、そのたびに古井さんの文章を参考にさせてもらった。
もう一つ忘れることができないのはロベルト・ムージルの「愛の完成」と「静かなヴェロニカの誘惑」の翻訳(1987年・岩波文庫)である。この翻訳は本当に素晴らしい。以前に古井さんは同じ作品を訳しているが(松籟社のムージル著作集に収録されている)、岩波文庫の訳は格段に良くなっている。ムージルについては『ムージル 観念のエロス』(1988年)と『ロベルト・ムージル』(2008年)というすぐれた作家論がある。
なんだかとりとめのない文章になってしまった。こういう評価はまだ早いかもしれないが、ぼくのなかでは夏目漱石とともに日本文学の最高峰という気がしている。漱石にはじまった日本文学の歩みが、古井さんによって一つの終焉を迎えたと言えるのでないかな。
写真は『文學界』新人賞をもらったときの新聞記事と掲載誌、記念品としてもらった時計。賞金は60万円だったかな? 10万円でCDプレイヤーを買って、残りは奥さんにあげたような気がする。