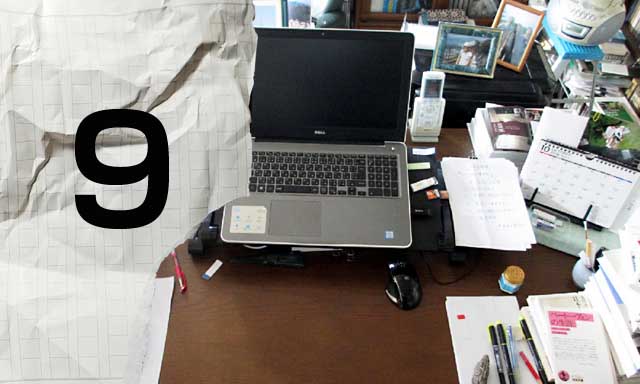つぎにぼくが夢中になった作家が、このあいだ亡くなった古井由吉さんだ。古井さんはぼくがいちばん影響を受けた作家といっていいだろうね。ずいぶん昔のインタビューで武満徹さんが、新しい作品に取りかかる前にバッハの『マタイ受難曲』を聴くという話をしていた。自分にとっては禊ぎのようなものであると。タルコフスキーの映画『サクリファイス』に触れてのことだったと思う。あの映画では冒頭で「神よ憐れみたまえ(Erbarme dich)」という『マタイ受難曲』のアリアが流れる。ヘルムート・リリング指揮でユリア・ハマリのアルトだ。
どうしてそんなことをおぼえているかというと、タルコフスキーの映画に打ちのめされたぼくは、映画館の帰りにレコード屋に飛び込んで3枚組のCDを衝動買いしてしまったからだ。そのころはCDも高くて1万円くらいしたと思う。あまりにも映画とバッハの音楽に感動して、前後の見境がなくなってしまったんだね。父の愚行のために幼い二人の息子たちはひもじい思いをすることになった、というのは嘘だけど。ちなみにユリア・ハマリの歌うアリアは、いまはYouTubeで簡単に視聴できる。映画のインパクトもあって、ぼくは彼女のヴァージョンがいちばん好きだな。

こんな話をしていたら、いつまで経っても本題に入ることができないけど、全然関係がないわけじゃない。というのも、ぼくにとって古井さんの小説は、武満徹にとっての『マタイ受難曲』みたいなものだからね。まあ、武満さんを引き合いに出すのはおこがましいけれど。小説を書いているとき、ぼくは机の端に古井さんの新刊を何冊か置いて、仕事をはじめる前に少しずつ読むことが多い。だいたい朝8時にコーヒーを持ってパソコンの前に坐る。そして古井さんの小説を何ページか読むわけだ。
近年の作品には『やすらい花』『蜩の声』『鐘の渡り』『雨の裾』『ゆらぐ玉の緒』などがあるけど、どれも粘性の高い日本語で、読むのに集中力と気力を要する。とても一気に読み通せるものではない。その点では『聖書』などに近いかもしれないな。ぼくの場合は数ページも読めば充分だ。読んでいるうちに、「さあ、今日も日本語を書こう」という気持ちになる。まさに日本語の森の奥で禊ぎをするようなものだろう? 日本語という言葉の精髄に立ち返らせてくれるっていうか。ぼくにとって古井さんはそういう作家なんだ。
ぼくが古井さんの作品と出会ったのは大学院生のとき。学部学生のときから拙い小説を書きはじめたことは前に話したよね。最初は大江健三郎さんの文体で書いていたんだけど、そのうちに物足りなくなってきた。文章を綴るときの呼吸は人によって違う。短い息をつないでいく人もいれば、長い息で一文を書く人もいる。そのころぼくが自分に合っていると思ったのは堀辰雄だった。『美しい村』や『風立ちぬ』などの作品が好きでね、この人の呼吸で書けば楽に文章が書ける気がしたんだ。リルケの『マルテの手記』を読んで惹かれたのも、堀辰雄と共通したものを感じたからだと思う。なんとなく、そのあたりに自分の資質を探り当てようとしていたんだろうね。
そんなある日、大学近くの古本屋で古井さんの『男たちの円居』を見つけた。講談社から出ていた単行本で、「雪の下の蟹」「子供たちの道」「男たちの円居」という三つの中編が収められている。いずれも芥川賞を受賞した「杳子」や「妻隠」が書かれる少し前の作品だ。「ああ、こんな小説を自分も書きたい」と思った。それからはもう一心に古井さんの文体を真似することになる。
写真はぼくの本棚で古井さんの本が詰め込んである部分だ。背後にもぎっしり入っている。文庫は別のところに置いてある。たぶん古井さんの作品はほとんど揃っているはずだ。こういう作家は古井さんだけだな。どうしてこんなことになったのかわからない。たんに好きってことだけじゃない気がする。そのあたりのことは、また来週考えよう。