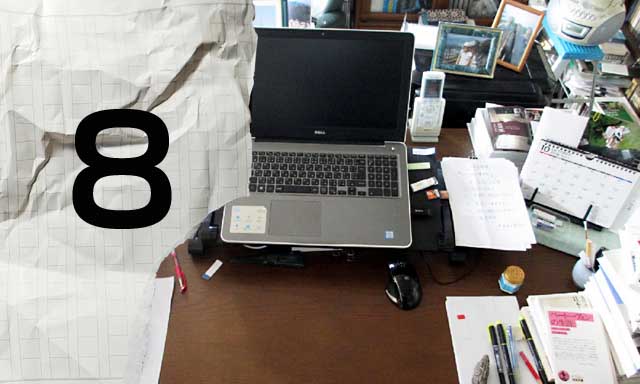ぼくが小説らしきものを書きはじめたのは大学2年生か3年生のときで、時代でいうと1978年から79年くらいになる。いろんな本を読むうちに、漠然と小説を書いてみたいという気持ちになったんだけど、前にも書いたように、最初の出会いが戦後派だから、小説っていうのは戦争のような特別な体験を題材にして書くものだろうと思っていた。この思い込みから自由にしてくれたのが大江健三郎だった。
大江さんのデビュー作は「奇妙な仕事」という作品で、これは大学で実験用の飼われていた犬を処分するというアルバイトの話。つぎの「死者の奢り」は、アルコール溶液に浸された解剖用の死体を新しい水槽に移すという、やっぱりアルバイトの話だ。いずれも舞台は大学で、仕事の相棒が女子学生ってところも共通している。殺処分される犬とか解剖用の死体とか、いかにも大江さんらしい題材が選び取られている。相棒の女子大生との会話によって小説の妙味をつくっているわけだね。

技量のほどは別にして、こういうものなら自分にも書けると思ってしまったわけだ。ぼくも大学に通い、アルバイトもしていたからね。同年輩の女の子だって知らないわけじゃない。実際にどういう小説を書いたのか忘れてしまったけれど、大江さんの小説を真似て書きはじめたはずだよ。彼が影響を受けたというサルトルの『嘔吐』なんかも読んだな。わりと面白くて気に入った。濃い霧が立ち込めたパリの描写とかね。同じく実存主義の作家といわれたカミュの『異邦人』なども読んで、これも面白かった。あとは『ペスト』とかね。
アメリカ文学ではヘミングウェイの『老人と海』なんかが好きだった。フォークナーとかソール・ベローやボールドウィンなども読んでいた。イギリスの作家ではアラン・シリトーとかね。こうやってあげていくと時代を感じさせるなあ。ボールドウィンやシリトーなんて、いまの若い人はほとんど知らないんじゃないかな。
アラブやラテン・アメリカの文学もわりと読んでいた。これは野間宏の影響だな。彼の編集した『現代アラブ文学選』(創樹社)という本がいまも手元にあるけれど、小説ではカナファーニーの「ハイファに戻って」などが収録されている。現在は「太陽の男たち」などとともに河出文庫で簡単に読めるからおすすめです。若くして爆殺されたパレスチナの作家だけど、「悲しいオレンジの実る土地」とか「彼岸へ」とか、いい作品が多い。
ラテン・アメリカ文学ではなんといってもボルヘスとマルケスだけど、他にもフエンテスとかリョサとか、たくさんいるな。とくに印象に残っているのはキューバの作家で、エドムンド・デスノエスの『いやし難い記憶』という作品。小田実の訳で筑摩書房から出ていた。いまは野谷文昭さんの訳が『低開発の記憶』というタイトルで白水社から出ている。ラテン・アメリカ文学はなんとなく肌に合うと感じた。ブラジルやキューバなどラテン・アメリカの音楽が大好きなのと関係があるのかもしれない。
あとラテン・アメリカ文学ではイザベル・アジェンデの『精霊たちの家』がおすすめだ。池澤夏樹さんが編集した河出書房新社の世界文学全集に入っている。ただ木村榮一さんの訳が、ぼくはもうひとつピンとこない。いまは入手が難しいかもしれないけれど、集英社の「世界の文学」に入っていたドノソの『夜のみだらな鳥』は、個人的にはラテン・アメリカ文学の最高傑作だと思う。
なんだか後半は世界文学案内みたいになってしまったなあ。写真は新潮社版の大家健三郎全作品。最初の6冊が黒のラベル。つづいてⅡ期が赤いラベルになっている。コンパクトな新書版で1976年の『ピンチランナー調書』まで、全小説が入っている。いまは活字が小さくて読むのが辛いけれど、一応処分せずに持っています。