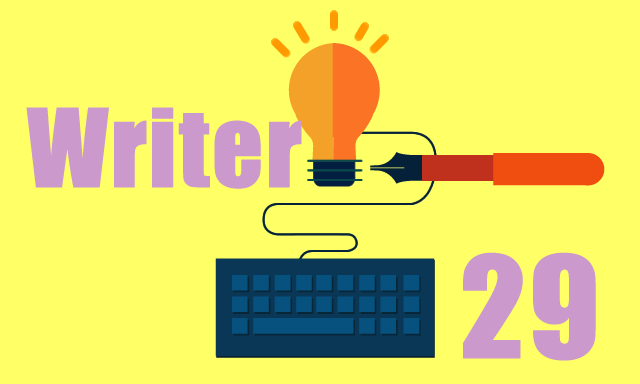ぼくが被った災難、つまり病気のことについては、まだいくらでも書くことができる。けれども書けば書くほど自分自身の気持ちが落ち込むし、読者にしてもあまり気持ちのいい思いはしないだろう。ただ、結果的にぼくはいまとても元気だし、精神的にも(ほぼ)健全だと言える。それはなぜか。そのことだけは記しておきたいと思う。
それは2009年2月の寒い朝のことだった。ぼくは一人暮らしがとても無理だということで、当時は姉のところで世話になっていたのだが、起き抜けのぼくに彼女はぽつりと言った。「母さんが亡くなったって」「そう」。ぼくは素っ気なく答えた。
何かしらの覚悟はできていたと思う。とにかく晩年は持病のリウマチをはじめ、さまざまな病魔に冒され、手術も何度も受けていた。明るい人だったが、自分の残された人生については悲観的で、「絶対に70代で死ぬ」みたいな話をよくしていた。そしてその予言は見事に当たり、76歳で逝ってしまったのだ。悲しいというよりも、なんというのだろう。「おつかれさまでした」という言葉をかけてあげることがいちばんなのではないか。そう思った。
葬儀は故郷の大分で行われたが、本当に寒い日で、遠くに見える久住の山々は雪化粧をしていた。その山肌から北風が吹き下ろすものだから、たまったものではない。分厚いコートを着ていても寒さが身にしみた。叔父や叔母たちにも久しぶりに再会したが、みんなぼくの病気のことは知っているとみえて、挨拶をかわすと「思ったより元気そうでよかった」と口々に言ったものだ。「はい、元気です。なんとか」とぼくも答えればいいのだが、まだ、そのころは、黙って微笑むことしかできなかった。
葬儀が終わり、火葬場に向かう車の中からも、ぼくは白く輝く山々をぼんやりと眺めてばかりいた。「母がもういない」。その現実はあまりにも実感が乏しく、骨を拾うときをむかえても、ぼくはまったく泣かなかった。ただ、どうしてかはわからないけれど、「がんばらないと」と、実に久方ぶりにポジティブなことを考えた。「もう、母はいろんな意味で助けてはくれない。だから、がんばらないと」。文脈からすればそういうことだったのかもしれないが、本当に久しぶりに、ぼくのベクトルは前向きに作用を始めていた。
薬が病気に対して奏功し始めていたこともあり、ぼくはそのころから次第に健康をとり戻していった。けれどもいまでもそうなのだが、読書ができない。それから映画みたいな長い映像作品を観つづけることができない。これはライターにとってはものすごくハンディーになるけれど、まあ、仕方ない。なんせ10年以上も病んでいたのだから。少なくとも以前のような、死への憧憬はきれいさっぱりなくなったし、暗い海溝の底にいるような絶望感も、日常的に感じることが減っていった。だから、母の死が直接のきっかけではないにせよ、母が亡くなったころから風向きが変わったことは確かだ。たいへんな時間を要してしまったが、ぼくは何とか海溝の中から光を見出そうとしていた。まさに失われた10年だ。ぼくはもう50代後半だけれど、この暗黒時代を差し引いて、厚かましくも、まだ40代のつもりでいる。