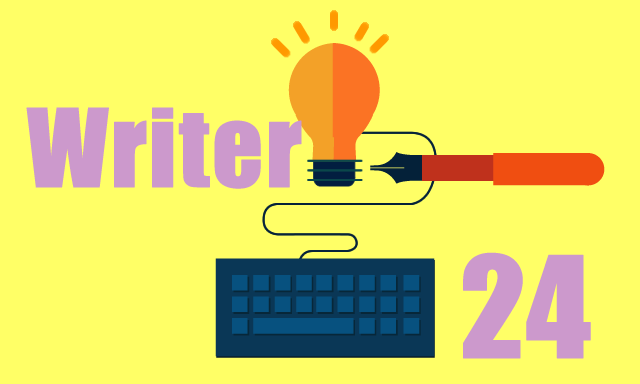ところでAという雑誌は、福岡県内のみで販売されていたのだが、ぼくが編集部にきて4年が経過したころだったと思う。名前をCという雑誌に改めて、中身を一新した(この雑誌はいまでも発刊されている)。ただ、それほど大きなリニューアルを果たした一方で、編集部の顔ぶれはほとんど変化がなく、9割がたは女性が占め、というより編集長のタドコロさんとぼく以外のスタッフは全員が女の人で、編集部内にいると何となく息苦しい気がしないでもなかった。
ぼくはP社を含めると、すでに6年ほどはこの業界に身を置いてきたので、若干、出世して、当時は編集チーフという立場になっていた。タドコロさんがH社の関連会社の社員になったこともあり、編集部に顔を出さない日が多くなってきたから、まあ、言ってみれば、その留守番役みたいなものだった。とはいえ、この留守番役というのが、なかなかキツかった。一旦、ぼくがO Kを出した原稿に、タドコロさんが赤字を入れたり、企画のツメの段階で一から考え直しになったりと、いわゆる中間管理職としての苦渋を味わうことになったからだ。もっとも当時はそれほど深刻には考えていないつもりだった。少なくともぼくの表層の意識の上では。ただ、この“苦渋”というやつが、ボディブローのように効いていたのは確かで、例えば円形脱毛症という形で、あるいは不整脈という形で、危険信号を発していた。それでも仕事はおもしろかった。企画を立てて取材に行き、それを文章にまとめるという作業自体が、無趣味なぼくにとってはいちばんのストレス発散法だと思い込んでいた。
そしてぼくは多忙なタドコロさんの代わりに、編集長になった。それはちょうど30歳のとき、95年のことだ。そしてこのことが、宿命的に後々、ぼくの人生に響いてくることになる。真綿で首を絞められるように。だから95年という年は、ぼくにとってはある意味でピークを迎えた年ということになるだろう。実際、このころに考えた企画であるとか、文章であるとか、そういう制作物を見ると、実に伸び伸びとやっていたなあと実感する。けれども現実には、転がる石のように、ぼくは勾配を下りはじめていたわけだ。尾根の長い山を降るがごとくと言ってもいい。知らず知らずのうちに、ぼくは底なしの谷に足を踏み入れてしまっていた。