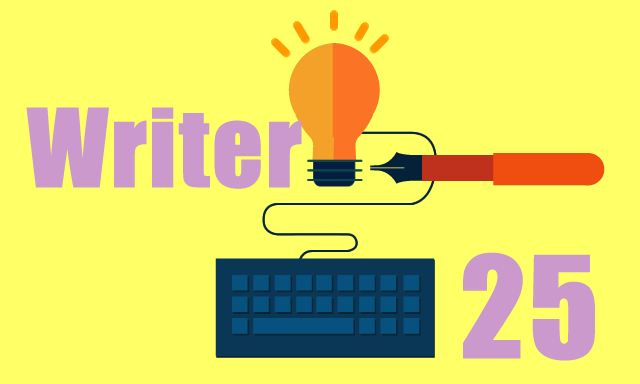自分が危険な領域に向かっていることなど知らずにぼくは仕事をつづけた。編集長には絶大な権限が与えられていたけれど、裏を返せばそれだけタフな業務だった。企画の立案はもちろん、マネージメントもミスの対応も情宣活動も…とにかく雑誌に関するすべてにおいてぼくは矢面に立たなければならなかった。これに加えてぼくはタドコロさんと同じように、H社の関連会社の正社員になった。もちろんそのことで待遇はぐっとよくなったし、社会的な信用度も高くなったと思う。けれども、徐々にその会社の中で、編集とは別の仕事も与えられることなった。帰宅時間もずいぶんと遅くなり、ぼくは自家用車で通勤をはじめた。ただ、誤解して欲しくないのは、ぼくは決して恨み言を述べているわけではない。何かを、つまり仕事を頼まれることは、ぼくにとってはうれしいことだった。何か言われれば、ひとつ返事で引き受け、決して断ったりはしなかった。ただ、人にはキャパシティというものがある。そしてそれを超えてしまうと、さまざまな不具合が出てくる。当然の結果として。
そのうちぼくは恐るべきというか、信じがたいというか、今までに感じたことがない倦怠感を抱えるようになっていた。とにかくカラダが重い。重くて仕方ない。まるで消波ブロックでも括りつけられているのではないかと思うほどだった。ときどき、どうしても耐えられなくなって、会議室の長椅子の上に横になったり、勤務中にネットカフェで仮眠をとったりすることもあった。何かが自分の中で起こっている。そんな状態になってようやく、漠然とそんなことを考えるようになった。そもそも、とぼくは思う。編集長なんていう激務はせいぜい3年が限度だと思う。結果からいえば、ぼくは結局6年間もこの任に就くことになったのだが。
それは編集長になって4年目くらいのことだったと思う。ぼくは人の勧めもあって、心療内科を受診した。そこでどんな検査をしたのかとか、どんなことを聞かれたのかなどということはすっかり忘れてしまったけれど「鬱」という診断が出た。何種類かの薬を出してもらい、しばらく様子をみるということになった。たしか、気持ちを前向きにする薬とか、睡眠導入剤とか、そういうものが処方されたと思う。ただ、この薬はぼくにはややヘビーだった。一日中、眠気がとれずに、カラダの倦怠感も改善しなかった。気持ちが前向きになるどころか、頭の中に濃いモヤがかかったみたいだった。けれどもぼくは仕事をつづけた。大袈裟かもしれないが、それこそ歯を食いしばって闘った。いまだから考えられることだけれど、このときに早めに休んでおけばよかった。そうすればぼくの人生は、もっとシンプルでクリアなものになったと思う。けれども帆船の水先案内人のように客観的になることができなかった。少なくとも「鬱」を病気として捉えていたなかったのだと思う。ぼくのメンタルはそんなふうにして少しずつ損なわれていった。