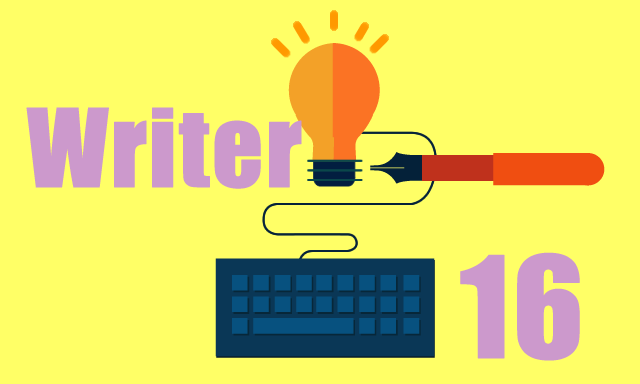長崎から帰ってきた翌日あたりだったと思う。ハマちゃんが写真を納品にやってきた。ワタナベさんとちょっぴり世間話をしたあとで、ハマちゃんはデザイナーのカワハラさんに「よろしくお願いします」と言って帰っていった。ぼくたちはさっそくハマちゃんが持ってきた写真を、ライトテーブルの上に載せてチェックした。「どうですか、カワハラさん」。ぼくは、黙って35ミリのポジフィルムを見ている彼女に質問してみた。「そうね」と彼女はすべての写真を見てしまうと、少しだけ笑みを浮かべて「まあ、いいんじゃない、ねえ、ワタナベさん」と言った。実を言うとぼくは写真に限らず、イラストやデザインなど、ビジュアル関係のことは、何を持っていいのか悪いのかを判断すればいいのかがさっぱりわからなかった。ハマちゃんの写真も、ぼくにしてみれば「さすがにプロのカメラマンはすごいなあ」とは思ったけれど、決して「使えない」などとは思えなかった。そういうこともあって、カワハラさんがなんとか気に入ってくれたことは素直にうれしかった。ハマちゃんと長崎の街を歩き回った同志として。
カワハラさんはぼくに「どうしても使わなきゃいけない写真に印をつけておいてね」と言って、ぼくに赤鉛筆を渡した。ライターは記事を仕上げるにあたって、必要になる写真のセレクトもやらなくてはならない。編集者とかディレクターと呼ばれる人が同行していれば、そんな仕事はしなくてはいいのだが、たかだかチェーンストアの機関誌だ。予算があまりないときには、ライターがその役割を兼務することは珍しい話ではない。もっといえば、そういうときには、ライターが取材の現場で編集者やディレクターの役割も果たさなければならない。もし、カメラマンが必要な写真を撮り忘れていたら、それはライターの責任になってしまう。なかなかの重責を背負っているわけだ。
カワハラさんはぼくが写真を選ぶとすぐに作業にとりかかり、レイアウト用紙にあらあらのデザインをした。文字数を出してもらったら「だいたい4500字くらいかな。よろしくね」と言ってちょっと笑った。ワタナベさんも「文字数が若干少なくなる分には、写真の調整でなんとかなるから気にしなくてもいいからね」と言ってカワハラさんと同じように少しだけ微笑んだ。「4500字か…」とぼくは心の中でため息をついた。原稿用紙にして約11枚にもなる“大作”を、果たして自分は書くことができるのだろうか。「まあ、考えてみれば、確か卒論は100枚くらいあったはずだ。あれをなんとか切り抜けたんだから、今回も大丈夫だろう、たぶん」。なんとも心許ない計算をして、ぼくはワードプロセッサの前に座った。
ライターになって何がたいへんかといえば、やはり、書き出しをどうするかということだろう。この仕事を始めたばかりのときも、短い文章にも関わらず、最初の言葉をどうするかでずいぶんと時間をとられた。しかし、そのとき書いていた文章と、これから書こうとしている文章は、なんというか質量が違う。ぼくはキーボードをなかなか打ち出せずにいた。