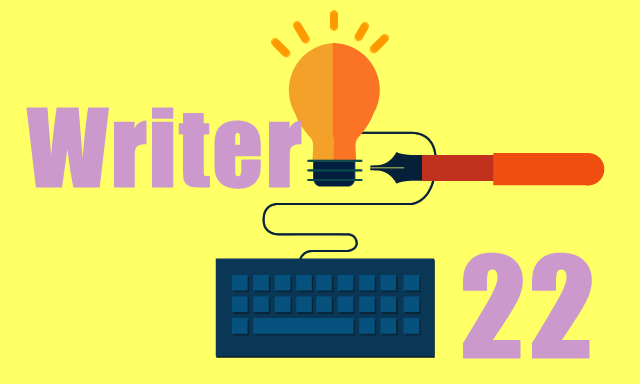今思えば愚かしい話だが、ぼくはその雑誌に載せる記事をひとりで書くのだろうかなどと思った。月刊紙で、しかもページ数も企画数もたくさんあるから、冷静に考えればそんなことは物理的にできるはずはない。ただ、ひとつにはその時若干酔いがまわってきていたのと、ひとつにはP社の機関誌の仕事では、ほぼ丸一冊分のライティングを担当していたので、そういう思い違いをしたわけだ。ぼくはもう少し酔いが身体中を包み込むのを待って、いちばん知りたいことをタドコロさんにたずねてみた。「あのう、ギャラはどれくらいになるのでしょうか」「うーん、たぶん20くらいになると思うけど構わない」「ああ、それはもう」。そのころのぼくは、よくて13万円くらいしか報酬をもらっていなかったので、ひとつ返事だった。これでかなり余裕が出る、そんなことさえ考えた。
しかし、タドコロさんはもっと驚くべきことを口にした。「まあ、がんばってくれさえすれば、一年後には倍は払えると思うよ」と。えっ、倍ってなんだっけ? あまりに驚いたのと酔いのせいで、ばくの頭は初期のMacのように瞬間的に固まった。待てよ、倍ということは40万? それはいくら何でもないのではなかろうか。実はP社の事務所で偶然、ウエキさんのギャラが書かれた書類を見てしまったことがあるけれど、かなりのキャリアを積んでいると思われる彼にしても月収は、確か30万くらいだったはずだ。仮にタドコロさんの言っていることが本当だとしたら、ぼくはウエキさんの報酬を一年で抜き去ることになる。ぼくは心を決めた。よし、やってやろうじゃないか。来年、40万もらえるように。ぼくの頭の中がシンプルすぎることもあるが、なんだかんだ言っても、お金というのは単純にモチベーションを上げてくれる。「わかりました」とぼくはタドコロさんに言った。「もう少し考えてから返事をします」。返事を伸ばす必要などなかったけれど、お金の話に釣られたと思われるのが嫌で、そんなことを口走ったのを覚えている。
後日、A編集部に入ることを決めたぼくは、タドコロさんとタクシーの中にいた。「いまからH社の上司に丸山くんを合わせるから、Aの編集がやりたいとはっきり言うように。実はFという機関紙の仕事を、同じクライアントからこの間もらったんだけど、彼はそれをきみにやらせたいみたいなんだよね」「そうなんですか」「そう、とにかく何かとうるさい人だから、自分の意見をハッキリ言わないと面倒なことになる」「わかりました」。タドコロさんはぼくの口数が少ないことを知って、そんな忠告をしたのだと思う。H社に着くとタナベさんという色が浅黒くてヒゲを蓄えた、いかにもバイタリティーの塊みたいな人を紹介された。「あなたが丸山くん、タナベです。タドコロからFの話は聞いてるよな」「はい」とぼくは答えた。「ただ、ぼくはAの編集がやりたいんですが」。そう言うとタナベさんは少し目を大きくしてぼくを見た。何だかそれだけでもぼくはある種の威圧感を覚えた。「おい、タドコロ、おまえちゃんと説明してくれてるよな」「はい、もちろん」。タドコロさんもどことなく“押されている”という感じだった。「じゃあ、聞いてると思うが、しばらくあなたにはFという機関紙の制作をお願いしたい。詳しいことはタドコロが話すと思うからよろしく」「わかりました」とぼくは答えた。「じゃあ、俺、打ち合わせがあるから」。タナベさんはそう言うと、もう踵を返して会社の奥の方へ移動を始めていた。ぼくはいろんな意味で圧倒されて、少々、不安な気持ちになっていた。