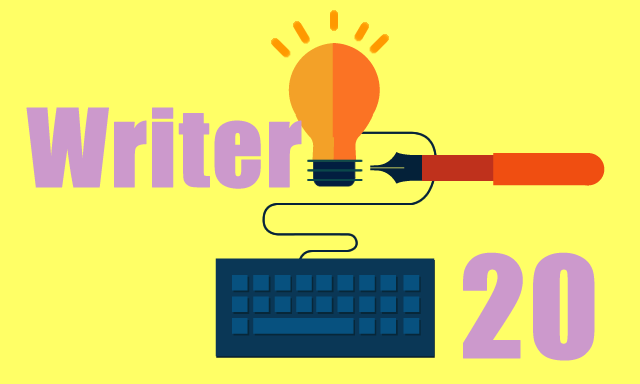その話がいつごろから出ていたのかはわからない。けれども、短時間で決まったわけではないことくらいは、当時のぼくにも想像ができた。チェーンストアの機関誌がタブロイド版に縮小されることが決まったのだ。「前みたいに予算がかけられなくなったらしくてね」とウエキさんは言った。「クライアントの売り上げが落ちているみたいで、まあ、仕方がないことではあるけど」「じゃあ、この事務所はどうなるんですか」とカワハラさんは言った。「そう、そこが問題なんだ。メインクライアントを失くすわけだから、このままだと福岡支社は存続できなくなってしまう」。ぼくはウエキさんのその言葉を聞いて、にわかに混乱してきた。ソンゾクできないって、つまりはクビってことだろうか。「会社はカワハラさんと丸山くんには残って欲しいと思っている。ただし勤務地は東京か長野になってしまう。もし、それでもよければってことだけど」「ちょっと考えさせてもらってもいいですか」とカワハラさんは言った。ぼくは黙っていたけれど、その言葉を聞いて大きく頷いた。同意という意思を示したわけだ。
「どう思います、ハマダさん」。あれは確か機関誌最後の特集取材のときだったはずだ。ぼくは移動の車中で、P社とぼくの将来のことを、カメラマンのハマダさんに相談した。「丸山くんはどうしたいの?」「そうですねえ、正直なところわかりません」「この先もライターをやっていくつもり」「うーん、それもなんとも言えませんね」「でも、P社には2年くらいいたわけだろ。いま、辞めるのはもったいない気がするけどなあ」「ただ、今さら(といっても、当時のぼくはまだ24〜25才くらいだった。何を考えていたんだろう)、東京だか長野だかに行くのもなんか面倒な気がするんです」「まあ、わからんでもないけどね」「ライターの仕事自体は好きなんで、つづけたいとは考えているんですが。どこか雇ってくれるところってありますかね」「そうねえ。まあ、ないことはない。今度、聞いてみてあげるよ」とハマダさんは言った。「ぼくもテレビ関係の仕事だったら、まったくあてがないわけじゃないんで、そっちもあたってみますね」。考えてみれば、このときのぼくは、それほどライターという仕事に執着していたわけではなかった。なにしろまだ若かったから、もっと条件のいい話があれば飛びついていたかもしれない。つまり、やりがいとかそういうことは二の次として。ただ、雑誌でもテレビでもいいのだけれど、できれば何かを制作する仕事には就いておきたかった。そのへんは譲れないというような気持ちを、なんとなくではあるが感じていたことは確かだ。
もちろん、ぼくはウエキさんにも相談をした。とはいっても、P社に居つづけるつもりはなかったから、それについては、あらかじめはっきりと伝えておいた。ぼくが相談したのは、ライターをつづけるべきかどうかということだった。「どうなんでしょうウエキさん。率直に意見を聞かせてほしいんですけど、ぼくはライターとしてこの先もやっていけるでしょうか?」「そうだなあ」とウエキさんは口髭の辺りを触りながらこう言った。「まあ、それは何とも言えないけど、努力次第だよね、何をやるにしても。でも、丸山くんはまだ若いから、別にライターにこだわる必要はないと思うな。要するにやりたいことをやればいい。それがライターだというのなら、つづけてさえいればモノになるんじゃないかな」「そうでしょうか」。ぼくはウエキさんが差し障りのない返事をしたことに、少なからずがっかりした。ただ、仮にこのときウエキさんが「ライターはやめたほうがいいよ」なんていうことを言ったとしても、「はい、そうですか」とは言わなかったと思う。なぜならP社を辞める日が近づくにつれて、ぼくはライターという仕事に魅了されていることに気づいてきたからだ。