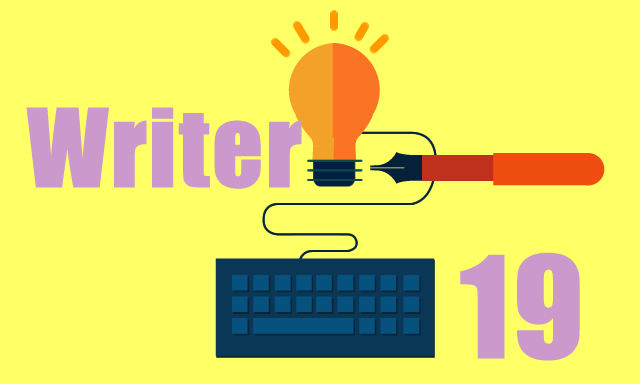ワタナベさんは4月になると、P社の異動で東京に戻ってしまった。そして後任にウエキさんという40歳くらいの人がやってきた。ウエキさんはデザイナー兼編集者で、以前はとある名の知れた週刊誌の編集に関わっていたらしい。無口な人だけれど、とてもクレバーな雰囲気を漂わせていて、実際、紳士的な人だった。考えてみるとこの頃のP社の福岡事務所は、ずいぶんと静かだったと思う。なぜって、ウエキさんを筆頭に、デザイナーのカワハラさんも必要以上のことはほとんど話さなかったし、ぼくもほぼ一日中押し黙っていたからだ。もちろん、それは機嫌がどうのということではなく、3人ともそういう性格だったから仕方がない。他のふたりはどう思っていたかは知らないけれど、少なくともぼくには居心地の良い空間だった。
ぼくは仕事の手があくと、資料やカメラ機材が置かれている和室の部屋でごろりとなり(この部屋はふすまで仕切られていた)、例の『太陽』をはじめ、さまざまな雑誌や書籍を読み込むことにしていた。まあ、早くいえばサボっていたわけだが、これはこれでライターとしてなかなかの滋養になったと思う。本はもちろんだが、雑誌だろうと漫画だろうと、とにかくたくさんの活字をなぞっていくことは、やはりライターには必要不可欠なトレーニングだからだ。ボキャブラリーやさまざまな知識や見識を備えてこそ、おもしろい文章が書けるようになるし、さまざまな書き手の手法のようなものも真似してみようかという気にもなってくる。そう、いわゆるクリエイティブと呼ばれる仕事は、この模倣から出発するのがいちばんではないだろうか。たぶん、その辺りがアーティストと位置づけられる人たちとは幾分ベクトルが違っていると思うのだが。
チェーンストアの機関誌が月刊だったため、“特集”の記事を書くことは、毎月のルーティーンのひとつだった。そして、ぼくはこの作業を、必ずウエキさんとカワハラさんが退勤してから進めることにしていた。つまりは徹夜をして書くことにしていたわけだ。いまは徹夜なんて考えられないが(そんなことをしたら体調がガタガタになってしまう)、当時はその方が仕事の効率が上がる気がしていたのだろう。近所の食堂で夕飯をすませ、少し休憩して、21時くらいからワードプロセッサの前に座り、少しずつ言葉を重ねていった。夜が更けてくると、だんだんと周りが静まりかえり、事務所の中はカチカチとキーボードをたたく音だけに支配される。このころがまさにランニングハイというか、頭の中が実にクリアになる時間だ。書いている内容はともかくとして、いつまでも、何千何万文字でも「書いてやるぜ」という気持ちになる。もしかすると、本当に脳内でエンドルフィンが分泌されていたのかもしれない。そうこうして朝を迎え、ちょうどウエキさんとカワハラさんが出社してくるころに原稿が完成する。そしてとりあえずは無罪放免。ひとつの仕事を終えたことを実感し、ぼくは家路につく。そして、その夜は例のキャバーンクラブへ行って、ビートルズを聴くわけだ。ブートレッグスのチャッピーさん、最高だったな。『ギターは泣いている』のクラプトンのパートはいまでも耳に残っている。赤いテレキャスがカッコよかった。
それから半年とちょっとはこういう平穏な生活がつづいた。人生を左右する重大な転機が迫っていることなど知る由もなく。