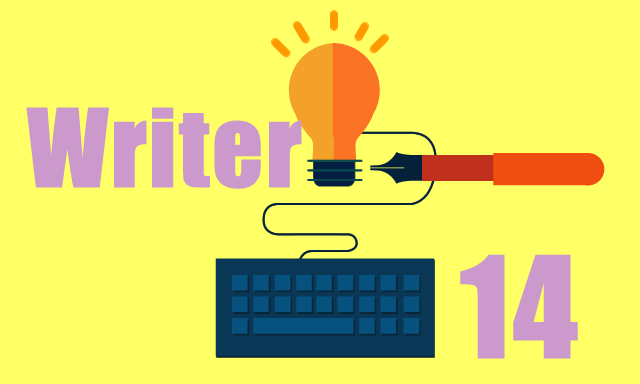ハマちゃんはカワノが言ったように、取材の前日に中華街へ連れていってくれた。もう、あたりは暗くなっていたが、きらびやかなランタンやライトアップされた極彩色の建物のおかげで、まったく闇というものを感じることはなかった。「ここがね、なかなか旨いんだよね」と、ハマちゃんは迷うことなく一軒の中華料理店に入った。確かに人気の店らしく、テーブルのほとんどはすでにうまっていて、ぼくたちは隅のテーブルへと案内された。「好きなもの注文していいからね。奢るからさ」とメニューを渡されたが、田舎者でもあるぼくは、いわゆる街中華で皿うどんを頼むくらいで、何だかよくわからない漢字で書かれた品書きを見てもピンとくるものがなかった。「ハマダさんにおまかせします」と言うと「そう」と彼は言って、店の人にビールと何種類かの料理を注文した。「はい、とりあえずおつかれさん」とハマちゃんは、(当たり前のことだが)慣れた調子でコップにビールを注ぎ、一気にそれを飲み干した。ぼくはいまでこそ、飲まない日はないけれど、当時はあまり酒には興味がなく、運ばれてくる料理が素晴らしく美味しかったので、しばらくは食べることに注力した。
気がつくとぼくは結構、酔っ払っていた。ビールを飲んで紹興酒のボトルを開け、そのときは確か焼酎を飲んでいた。ぼくは酔いにまかせてこの職業についていちばん疑問だったことをハマちゃんにたずねてみた。「ライターやってて、そのうち喰えるようになるんでしょうか。ぼくもいつかは誰かに酒を奢ってあげたりできるようになるんでしょうか。どう思います」「ああ、金のことか、金はね、そのうちなんとかなるから心配しなくてもいいよ」とハマちゃんは言った。「なんとかなるって言っても」「大丈夫だって。金はあとからついてくるから、いまは真面目に仕事してればいいの」「そうでしょうか。ぼくは書くことは嫌いじゃないけど、あまりになんていうか、ギャラが安すぎて…」。ハマちゃんは苦笑しながら言った。「まあ、丸山くんはまだ仕事始めたばっかりだろ。いくらもらっているのかは知らないけど、大企業にでも入らない限り、最初から喰える奴なんていないって。ただね、不思議なことにつづけてさえいれば不思議と金は入るようになる。そんなもんだよ、この世界って」「そうですかね」「そうだよ、俺だって嫁さんと子どもを養えるくらいにはなったんだから」。ハマちゃんは空になったぼくのグラスを見て言った。「もう少し飲む?」
このときにハマちゃんから示唆されたことは、いま思えば確かに3分の2くらいは当たっていた。しかし、あまりにも話が抽象的かつぼんやりしていたので、正直なところ当時はすぐに咀嚼できなかった。ただ「金はあとからついてくる」という一言だけは、なぜだかすごくインパクトがあって、彼の名言というか迷言として頭の中に残っているし、ぼくも受け売りでそんなことを誰かに言ったような気もする。ぼくは翌日の早朝から取材ということを忘れ、結構な量の酒を飲んだ。ホテルに帰ると着替えもせずに、ベッドに倒れ込み、泥沼のように眠ってしまった。