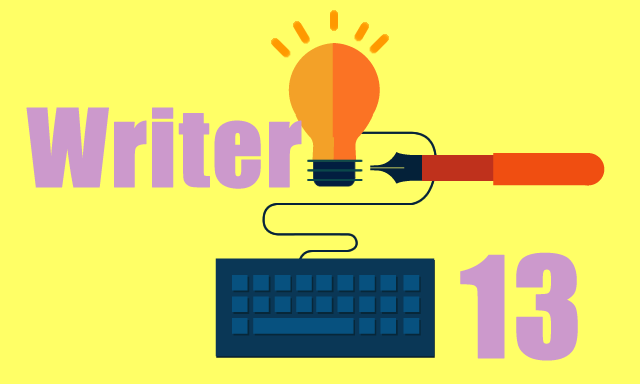ぼくが担当することになった機関誌の“特集”は、文字数がだいたい4000字強くらいあった。もちろんいまではそんなことを聞いても驚きはしないが、それまで、せいぜい1500字程度の文章しか書いたことがなかったから、結構なボリュームというより、ある意味それは未知の領域だった。取材の内容は長崎の路面電車をテーマに、市内の観光案内などをするというものだったが、言うまでもなく、そんな紀行文を書くのも生まれて初めてのことで、取材の日が近づくにつれて、ぼくはだんだんと緊張してきた。参考書としてきた雑誌の『太陽』を引っ張り出して、似たような文章がないか注意深く読んでみるのだが、頭にあまり入ってこない。ワタナベさんはそのころまだ福岡に居たから、アドバイスをお願いする手もなくはなかったが、何だかそれも億劫でやめておいた。
そうこうしているうちに、カメラマンのハマダさんとの打ち合わせの日がやってきた。と言っても、ワタナベさんが簡単な企画書を渡して、取材の要点だけ伝えるというもので、ごく短時間で終わった。「ハマダさん、今回はちゃんと撮ってきてくださいね」。一緒に参加していたデザイナーのカワハラさんがそう言った。彼女は特集の誌面レイアウトを担当していたのだが、写真には厳しい人で(これはデザイナー全体に言えることだが)、若干、ハマダさんの腕には“疑問”があるようだった。ハマダさんは苦笑いしながら「わかってますよ、がんばってきます」と答え、「丸山くんも特集初めてなんだよね。一緒にがんばろうね」とやや軽い口ぶりで話しながらニヤリとした。「まあ、二人いれば何とかなるよ。ぼくから言うことは以上」とワタナベさんも細かいことはあまり気にしていないようだった。いま思えば、そんな適度にいい加減な打ち合わせでよかったと思う。雨が降ったらどうするだの、取材先のアポイントはちゃんととれるのかとか、世の中にはやたらとネガティブなことばかりを気にする人がいる。経験上、こういう人たちとの打ち合わせは時間が長くかかるし、得るものは少ないしで消耗ばかりするものだ。「じゃあ、丸山くん。当日はよろしくね」とハマダさんは言った。「楽しみにしてるよ」とニヤニヤしながら「じゃあ」と言って事務所をあとにした。おかげでぼくの緊張もかなりほぐれて、「確かに二人で行くんだからなんとかなるか」という気持ちになってきた。
4人暮らしの自宅に戻ってくると、ハマダさんのアシスタントのカワノが「聞いたよハマちゃんから。特集の取材で長崎だってね」と話しかけてきた。「まあね、ハマちゃんもいるから何とかなるんじゃないかな」。ぼくたちはハマダさんのことを本人がいないときはハマちゃんと呼んでいた。「なんかおまえを中華街に連れていくんだって張り切ってたよ」「へえ、いいなあ中華街。もちろん奢ってくれるよね、ハマちゃんが」「それはそうじゃない」「だよね。俺は今月の給料10万だったし」とぼくは言った。世はバブル全盛のころ。しかし、駆け出しのライターにはそんな話は無縁だった。いや、いまでも言えることだが、金儲けが目的ならライターはやめたほうがいい。ユーチューバーにでもなることをおすすめする。