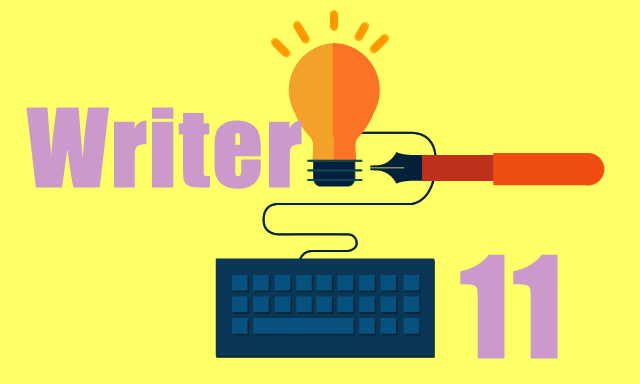ワタナベさんがいなくなる。ぼくはぼくの“師匠”である彼が、いなくなってしまうということを考えると不安な気持ちになった。なぜなら、彼はぼくが苦手な上からガミガミ言ってくるようなタイプではなかったし、それどころかいろいろと新人のぼくに気をつかってくれていて、そう言う意味でとても親切な人だった。もちろん、ぼくが書いた原稿に対してのアドバイスも的確だったし、説明もわかりやすかった。おかげでP社に入社して半年あまりが経ったこの頃には、原稿にほとんど赤が入ることはなくなっていたし、真面目に仕事さえしていれば、組織に縛られているような窮屈さを感じることもなかった。デザイナーの女の子の一人が言った。「今度はどなたがいらっしゃるんですか?」「うん、4月からはウエキさんっていうデザイナーの人が本社からやってくるらしいよ」とワタナベさんは答えた。「ライターじゃなくてデザイナーなんですか」「そう。まあ、デザイナーと言っても、編集全般に長けた人だから、仕事のことなら何でも答えてくれるはずだよ」。ぼくは思い切ってワタナベさんに聞いてみた。「そのう、ぼくはどうしたらいいんでしょうか?」「ああ、丸山くんも心配しなくてもいいよ。いまの調子で書いていけば、たぶん、たいていの仕事はこなせると思うから。ただね、ぼくがいまやっているライティングの仕事は、丸山くんに担当してもらおうと思っているんだけどいいかな」「もしかして特集もですか」「そう、特集も」
“特集”というのは、例のチェーンマーケットが発行している機関紙の巻頭記事のことだ。九州内のいろいろな場所を取材して紹介するという、まあ、わかりやすく言えば紀行文を書けばいいのだが、もちろんそんな仕事はやったことがない。「ぼくにできるでしょうか?」「大丈夫、丸山くんにならできるよ」「そう、ですか…」「とにかくやってみてくれないかな。4月号の長崎取材からお願いしたいんだけど」「はあ…って、もしかして撮影もですか?」「いやいや撮影はカメラマンが一緒だから心配しなくてもいいよ。丸山くんを紹介してくれたハマダさんっていう人が行くから。今度一緒に打ち合わせしようね」
ハマダさん。彼はワタナベさんとほぼ同年齢で30歳過ぎくらいだったと思うが、ぼくの同居人が彼のアシスタントをしていたことからP社を紹介された。面識はなかったが、「カワノ、飲みにいくぞ」と言って、一度アシスタントの友人を夜中に呼びにきたことがあった。つまりカワノというのがその友人なのだが、夜中の3時くらいではなかっただろうか。同居人たち4人で寝ていた部屋に、ズカズカと押しかけてきたのがそのハマダさんだった。「P社の丸山です」と確かそのとき挨拶だけはしたと思う。したとは思うが、なんせ時間が時間だから、部屋の明かりは消していたし、ぼくも寝ぼけていたしでほとんど覚えていない。けれども、これはあとでわかってきたことだが、酔っ払うとそういう非常識なことをたまにやらかしてしまうのがハマダさんという人だった。それでも不思議と憎めないところがあるのも彼で、人脈も広かったと思う。そしてぼくのライター人生の始まり、そしていまがあるのも彼のおかげだと言える。そのことについてはまた後で書こうと思う。